【日米学生会議との出会いと参加理由】
本日はどうぞよろしくお願いいたします。天野様は、どのように日米学生会議を知り、応募を決意しましたか。また、当初は会議に対してどのようなことを期待していましたか。
私は終戦を満州の鞍山中学校で迎え、その後に秋田の実家へ戻りました。戦争で良い思いはしておらず、当時は百姓として働きたいと考えていましたが、結局は勉強することになりました。1951年にはサンフランシスコ条約が調印され、敗戦後の日本は国際社会での生き方を真剣に考えなければならない時代でした。その頃、日本の外貨準備はわずか8億ドル、輸出20億ドル、輸入24億ドルしかありませんでした。その為には何が何でも輸出を増やして、国にとって必要な輸入を実現しなくてはいけない。それは必然的に国際問題に繋がる議論になります。国内だけを見ていても仕方がないのです。日本の復興と国際社会への復帰が最大の関心事でした。このような状況の中で、学生たちの間でも国際的な関心が高まっており、日米学生会議の母体であるInternational Student Associationには各団体が興味を持っていました。
私が具体的に日米学生会議への参加を決意するきっかけとなったのは、大学の国際部、今で言うところのESSで、ジャーナリストのアズベリさんという方に出会ったことでした。アズベリさんは私のJASC参加にあたって、ディベートの指導などをしてくださりました。私が参加したのは1951年に開催された第12回日米学生会議で、日本側の代表は小林氏(慶應大学名誉教授)であり、アメリカからはキッシンジャー氏も代表として参加していました。
第二次世界大戦直後で国際的な調和が求められている状況でした。私たちは国を挙げて国際的な協調を行う必要性を感じていました。日米学生会議を通じて、異なる国の学生たちと交流し、国際問題について深く議論することで、将来の世界の調和に貢献したいという思いを抱いていました。日米学生会議への参加は、私にとって非常に貴重な経験であり、その価値は今でも続いています。
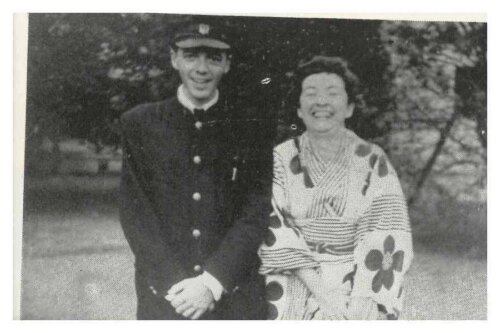
アズベリさん(左)

【第12, 13回日米学生会議から得たもの】
第12,13回日米学生会議では、どのような経験が得られましたか。一番印象に残り、現在に つながる学びはありましたか。
1951年に開催された第12回日米学生会議は、学習院大学を会場にし、日本側85名、アメリカ側55名、計140名の学生が参加しました。この会議では、「講和条約締結後の日本」というテーマで議論が行われました。翌年に開催された第13回では、早稲田大学、藤女子短期大学、アメリカンスクールが会場となり、日本側176名、アメリカ側177名と、前年を大きく上回る計353名の学生が参加しました。
第8回から第14回までは毎年日本で開催されていたのですが、1954年開催の第15回では戦後初のアメリカ開催の年で、日米両国の学生たちがコーネル大学に集いました。しかし、その後は資金不足のため、1964年までの10年間、日米学生会議は中断されることとなりました。当時は、海外に出るためには特別外貨が必要であり、そのような時代背景もありました。実際にアメリカの学生と対面して議論をし、共同生活を送る中で、異文化の違いを感じる貴重な経験をしました。また、日米学生会議の代表に在日の米国人を選出するという議論もありました。
会議参加を通じて、やはり国際交流の重要性を痛感しました。異なる文化や背景を持つ学生たちとの議論や交流を通じて、自身の視野が広がり、国際問題への理解が深まりました。
これらの学生会議から得た最も大きな学びは、協調性と対話の重要性です。異なる意見や価値観を持つ人々との対話を通じて、相互理解を深めることが必要であるということを学びました。また、異文化の中で自分自身を見つめ直し、自己成長する機会でもありました。現在でも、このような国際的な交流の経験が私の人生において大きな影響を与えています。日米学生会議を通じて得た貴重な経験と学びは、私の人生の中で首尾一貫した価値を持ち続けています。

印象に残っている米国側の参加者はいらっしゃいますか?
私の参加したCulture分科会に、米国側から宣教師の方々が2名、バーローさん、レインさんが参加していたことが、私にとって印象的でした。「絶対者たる神は存在するのか」という神の存在証明についての議論を、皆で真剣にしたことを覚えています。また、別の機会には、著名な伝道師であるビリー・グラハム氏が来日した際、階段教室での伝導会にも招かれ、参加したことがあります。この時には周りの人々がグラハム氏の帰依への呼びかけに応じて次々降段、入信していました。自分は却って反発して入信せず、このお二人を失望させてしまいましたが…。
また、ある米国側の参加者の言葉が特に印象に残っています。「if only we had Russian delegates…」(もし私たちにロシアの代表がいたならば…)という言葉でした。この言葉からは、冷戦構造が深まる戦後の国際社会においてこそ、互いの考えや状況についての理解を深めるためには、ロシアという言わば敵国を含めた様々な国の学生との交流が重要であることが伝わってきました。まさに満州事変の勃発を受けて、1934年に日米学生会議が興ったようにです。もし全ての国から学生が参加する学生会議を開くことができれば、国際的な相互理解と世界平和へ貢献できるのではないか、と考えていました。
第二次世界大戦後、ヨーロッパの大学では学生が自由に交換留学できる制度がありました。その結果、異なる国の学生たちが自由な議論を通じて戦争の意義や原因について議論する機会が生まれ、お互いの相互理解を促進しました。例えば、イギリス人とドイツ人の間では、「我々はなぜあのような戦争をしたのだろうか」といったことが議論されます。学生の間での、何のバイアスも無い真摯な議論というのは非常に貴重です。こうした本音の、忌憚ない議論を通して、「なんであんな良い奴がいる国と私たちは戦争したんだろう」という率直な想いが学生の間で生まれていきます。学生たちの間で生まれるこうした思考は、国際的な理解を深める上で非常に貴重なものでした。
第二次世界大戦後の激動の国際環境の中で、将来を担う学生たちの間で行われた議論は、私にとって非常に貴重な経験でした。国境を越えた交流と対話を通じて、私たちは互いの文化や価値観を理解し、共に成長することができることを学びました。
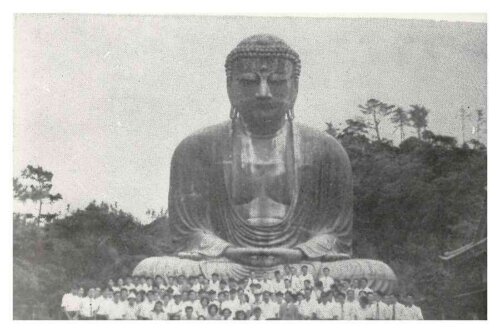
日米学生会議への参加を通して、ご自身の中で価値観の変化はありましたか?
まず、戦後の時代においては、日本がアメリカに敗北したという厳然たる現実がありました。
戦中はお互い「こんちくしょう」という感じで、敵意を抱くような状況でした。戦中の日本では、まさしく「鬼畜米英」という風潮が広まっており、国民の間には「何が何でも勝つんだ」という雰囲気がありました。
しかし、戦後はそれとは全く違う雰囲気に変化しました。戦後の社会の変化の中で、日米学生会議では、人間が生きる上で本質的な議論を行うことができました。当時の日本では、外国人を見るとアメリカ人かそれ以外かの違いなど分からない程度の国際的な知識しかありませんでした。
そのような状況の中で参加した日米学生会議を通して、外国に対する拒否感、馴染みの無さ、心理的距離が消えていきました。本音での議論と共同生活を通して、「彼も人なり、我も人なり」といった想いが芽生えていったんです。現代においても、責任ある政治家は、「彼も人なり、我も人なり」という考え方を持つべきだと思います。つまりはお互い相手にしているのは自分と同じ人間なのだ、ということを先ず、そして是非、心から大切にしてほしいと思います。
昔とは大きく変化した現在の国際社会においては、日米だけでなく、中国との議論も必要不可欠です。お互いの利害関係を冷静に把握し、学び合う姿勢が求められます。政治的立場を超えて、要は人間と人間の裸の関係が存在するということを、どれだけ真摯に捉えられるか。「live and let live」というように、共に生きる、共生関係を築いていくことの重要性を知ること、またそういう気持ちや感情を持つこと。 偏見に囚われないで、真摯に素直に相手と対峙することが重要だと思います。
第13回への参加は、様々な縁によって実現しました。三菱銀行の山室さんからのお誘いや、幹事長を誠心誠意やってくれた、中瀬正一さん、山本東生さん、大高巽さん達との出会いなどなど、その後の人生でも長く付き合うことになる友人との接点がありました。
私は日米学生会議を継続するために、これらの出会いを大切にし、今後も国境を超えた交流や対話を通じて、世界とのつながりを深めていきたいと思っています。価値観の変化を通じて、お互いに尊重し合い、共に成長していくことの重要性は、今でも深く心に留めています。
【日米学生会議での経験とその後の進路について】
大学卒業後のキャリアを歩まれるにあたり、日米学生会議での経験や、そこで得られた人の繋がりはどのように生きましたか。
1955年に一橋大学経済学部を卒業した後、私は第一物産株式会社(その後の二社合併で三井物産)に入社し、貿易に携わってきました。そして、修業生制度と言うのがあり、1957年にロンドンへ渡り、学びの機会を得ました。ハル大学かノッティンガム大学(シャーウッドフォレストにあるロンドンに近い大学)のどちらかに進学することになりましたが、正直どちらがどのような選択肢なのかよくわかりませんでした。最終的に私はハル大学に進学することになりました。
ハル大学は、イギリス中部辺りに位置するヨークシャーにある大学で、そこで経済学を学びました。教授たちとは週に一度、パブで会って話をするという関係でした。休暇の期間にはロンドンで働くこともありましたし、ノッティンガムにも少し滞在したこともありました。ノッティンガムは緑豊かな場所で、とても素敵な経験でした。ノッティンガム大学では1ヶ月ほどフランス語の勉強もしました。ハル大学での留学生活では、ブリティッシュカウンシルの紹介でヘイルストン夫妻のお宅に下宿していました。彼らの娘さんが農業大学に行っている間、彼女の部屋を借りて過ごし、学期が終わるとロンドンに移りました。
日米学生会議での友人たちとは、その後のキャリアの中で何度も交流する機会がありました。ニューヨーク時代に訪ねてくれる友人も多くいました。帰国後、役員を務めた際には、山室さんや中瀬さんとも再び出会いました。現役で働いている間は一生懸命に仕事に取り組んでいましたが、久しぶりに再会すると、皆が日米学生会議という共通の原体験を通して得た共通認識を持っていることを実感しました。「live and let live」という考え方です。
日米学生会議での経験やそこで築かれた人間関係は、私のキャリアにおいて大きな役割を果たしました。異なる背景を持つ人々との議論や共同生活を通じて、相手を尊重し、共に成長していくことの重要性を学びました。また、国際的な視野を持ち、相互理解を深めることの重要性も痛感しました。
日米学生会議の精神を心に留め、これからも人とのつながりを大切にし、お互いを尊重しながら生きていきたいと思っています。また、日米だけでなく、他の国との議論や交流も重要だと感じています。相手の利害関係を冷静に捉え、人間同士の関係を真摯に受け止めることが求められています。日米学生会議は私にとってやはり貴重な経験であり続けており、その価値は私の進路や人生の中で一貫して生き続けています。

日米学生会議の参加の経験が、仕事に繋がったこともあったと伺いました。
仕事における態度は、日米で正反対であり、両極端です。日本では上から指示されたらすぐに行動する傾向がありますが、アメリカではお互いに納得しない限り行動しない傾向があります。当時日米学生会議に参加したアメリカの学生たちの感想としては、「日本の学生は非常に真面目である」とか、「日本の良いところを日本人はもっと評価すべきだ」という意見がありました。
私自身も、長いキャリアの中で20年近くの海外生活を経験してきました。最初はロンドンで暮らし、その後はヨハネスブルグ、サンフランシスコ、トロント、ニューヨークなどで働きました。ニューヨークで働く前には、あるカナダ人の秘書から「ニューヨークは危ないから気をつけてください」と忠告されたこともありました。
日米学生会議を通じて、そして海外での勤務を通じて学んだことは、「外国に行ったら、主張することをビシッと最初に伝えることの重要性」です。これは、日本の学生がアメリカの学生から学ぶべきことの一つだと思います。日本の学生は暖かく思いやりがあり、親切で謙虚なイメージを持たれています。このような人間的な性格の両極端を、学生時代に体験することの重要性は非常に大きいものがあると思います。
例えば、イラク戦争の時、私はニューヨークで米国法人の社長をしておりました。
NYの名門ゴルフコースとされているSleepy Hollow Country Clubでの members tournamentの時のことです。後ろのグループにイラクからの凱旋米軍の大々的歓迎パーティー推進役の立役者となっている会社の社長がいました。同社からの寄付協力を我社が断った直後の事で、担当部門は商売を切られるのではないかと心配していました。
それで、私は後ろからその社長が上がってくるのを待ち、同社長にイラク戦争に関連して、日本国憲法第九条の説明と、この戦争に日本は国内では批判する向きもある程の血税を供出している旨、そして私自身は正直言ってこの戦争が果たして正しい判断か自信持てない苦衷も正直に吐露しました。結局、’We agree to disagree’となり、’Business as usual’とも合意し、’Let’s enjoy golf anyway’と別れました。
このように、私は本音として言うべきことや主張すべきことをはっきりと述べましたが、これは心情の違いによるものであり、会社とは関係ありません。主張すべきことをはっきりと主張することの重要性を感じる経験でした。
【応募者へのメッセージ】
最後に今後の会議に参加を希望する学生に向けてメッセージをお願いいたします。
日米学生会議は、太平洋をまたぐ世界的な無形文化遺産だと私は考えています。この会議を通じて、日本とアメリカの関係の複雑さを感じると同時に、日米のともがきを持つことの大切さも肌で実感しました。
また、日米学生会議は単に日米の交流だけでなく、同時に世界学生会議としての意識も持つべきだと思います。未来の世界のリーダーたるもの、全世界に共通した世界市民としての共通の意識を持つことが重要です。人と人の関係の基本は「live and let live」です。戦争は二度と起こしてはならない。
さらに、日米学生会議に応募する学生には、日米学生会議の良さや楽しさを吸収するだけでなく、自国のことをよく学んでから参加してほしいと思います。お互いがまず自国のことをよく知ることが必要です。しっかりとした議論の土台を築いてから参加してほしいと思います。
山本東生幹事長が精魂込めて完成してくれ、私にとってはJASCのバイブルでもある日米学生会議70周年記念誌に、第1回参加者の中山公威さん(当時92才)が次のように書かれています。
「現在の世界の情勢は政治、経済、環境にしても混沌とした様相を呈していることは誰の目にも明らかであります。人間の叡智をもって文化文明科学が発達した21世紀でさえ人類が過去に何度も経験した戦争や殺戮が世界各地で繰り返されている今日、また、国内に目を向けても不安と焦燥という形容が相応しい社会になりつつある今日、これら現象は人間が巡ってきた必然の結果であり、私達、人間が先ず変わらなければ社会(世界)は変わらないことを示している兆しであると思います。私がこの齢で信じていることは、世界平和は社会を構成する我々一人一人の心の中に先ず平和が育たなければならないということであります。その為には一人一人が自己中心的利己心を捨て美しい真心・良心を磨き出し、心の中に平和を築くことが構成する家族や社会に平和をもたらすと確信している次第であります。・・・この日米学生会議が今後とも会を重ねながら、お互いの相互理解や自己研鑽の向上と同時に、人の心に平和のともし火を灯す切っ掛けとならんことを祈念いたします。」
価値観をぶつけ合い、侃侃諤諤の議論のなかで、互いに切磋琢磨する。ぶつかった上で自分の中でそれを咀嚼し、更に相互理解へ繋げていく。フレッシュな頭脳と瑞々しい感性を持つ学生時代においてこのような体験をすることは、その後の人生観、そして人生そのものに大きく影響を与えます。中山さんのこの含蓄ある言葉の中にこそ、JASCerに共通するDNAの源泉が表れていると思います。JASCerたちに共通するDNAは、相互理解しようとする善意、向上心、そして世界平和の理想に一歩でも近づこうとする現実的な対応です。日米学生会議にこれから参加する皆さんには、真摯な議論の場を持ち、このJASCerのDNAを受け継ぎ、育み、複雑さと混迷を極める現代の国際社会において平和の礎を築いていって欲しいと思います。